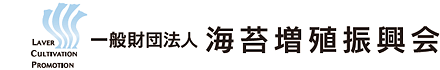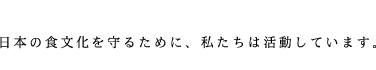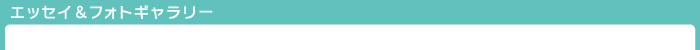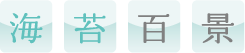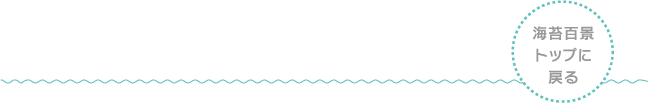一方、陸上植物では植物ホルモン(オーキシン、サイトカイニン、ジベレリン、アブシジン酸など)が生長や形態形成に関与することが知られており、これらホルモンの組織内での局在性や濃度の違いが形態形成を制御するとされている。言い換えれば、細胞分裂する場所や速度の違いが葉の形を決めているというのだ。例えば、若い丸っこい小葉が生長する時には、生長が部分的に促進されたり、部分的に抑制されることで出っ張りやへこみが形成される。出っ張りが強く出るためにはオーキシンが重要な役割を果たしている。また、ある種の葉(カエデやサクラなど)の縁に見られるギザギザ状(鋸歯)の形態はオーキシンとペプチド様ホルモン(EPFL2; Epidermal Patterning Factor-Like 2)の局在性と濃度勾配のバランスにより形作られているらしい。つまり、両者は互いにフィードバック制御(一方が他方の働きを抑制する)の関係にあり、EPFL2は鋸歯の先端部では作られず、裾野部分でのみ作られるため、EPFL2が発現しているとオーキシンは先端部に高濃度局在し、鋸歯が形成される。EPFL2が発現していないとオーキシンは裾野部分にも広く分布し鋸歯が形成されない。この形態形成に関与するオーキシンは植物自身で生合成されるものの他に、共生細菌に由来するものも存在するとの報告に興味がもたれる。なお、濃度勾配を作り上げるにはオーキシンやEPFL2に対する各受容体タンパク質の発現制御も必要で複雑である。
上記の陸上植物における研究例から、陸上植物と同様に海藻においても関連遺伝子やホルモン様物質による遺伝子発現制御によって「形」を作り上げているのか、知りたくなる。褐藻ヒバマタ(Fucus distichus)やシオミドロ(Ectocarpus siliculosus)にはオーキシンが存在し、前者では仮根形成に後者では分化・生長に関与することが報告されている。シオミドロにはオーキシンが作用誘導する遺伝子も同定されているが、陸上植物におけるオーキシンのシグナル伝達系とは異なるとのことである。しかし、その他海藻中の植物ホルモンについては分化、生長との関係から調べられた研究例は少ないようである。最近になりスサビノリやウシケノリ(Bangia fuscopurpurea)においてはオーキシン、サイトカイニン(N6-(Δ2-isopentenyl)adenine)、アブシシン酸、サリチル酸は存在するが、ジベレリンやジャスモン酸は存在しないこと、ゲノムワイド相同性検索から上記紅藻には陸上植物と同様のサイトカイニンおよびアブシシン酸合成遺伝子の存在は確認されたが、オーキシン合成遺伝子は検出されないことが報告された。したがって、同藻体内のオーキシンは共生細菌に由来している可能性が示唆されている。なお、これらウシケノリ科紅藻は上記の4種植物ホルモンの受容体遺伝子はもたないことから、陸上植物とは異なるホルモン作用機構の存在が予想されており興味深い。海藻中の共生細菌は陸上植物の場合と同様に着生細菌(epiphyte)と内在細菌(endophyte)の二通りが存在するが、細菌が提供する外因性植物ホルモンはどちらの局在菌に由来するのか、あるいは両方に由来するかは現時点ではよく分かっていない。もちろん、海藻自身が植物ホルモン生合成系遺伝子を共生細菌から水平伝播により取り込んでいる可能性もある。このように、紅藻における植物ホルモンの生理学的研究例は数少ない。ゲノム情報があるスサビノリやチシマクロノリにおいては植物ホルモン生合成関連遺伝子のゲノムワイド検索から、サイトカイニンはこれら紅藻ではin vivo合成されると推定されている。今後、新規に発見された形態形成誘導物質や従来型植物ホルモンについて、化学生物学的手法やゲノム情報による情報生物学的手法などを用いた機能解析が進み、海藻の「形」が作られる仕組みが明らかになることが期待される。
海藻に見出された共生細菌や同細菌が作る外因性物質が藻体の形態形成に役立っていることが判明しつつあるが、同じように陸上植物においても共生細菌が形態形成に関与しているのか興味が湧いてくる。陸上植物も組織の無菌培養下ではカルス状の形態を取る例が良く知られている。陸上植物も緑藻におけるサルーシンのような細菌由来の新規形態形成物質の恩恵を受けているのだろうか。加えて従来型植物ホルモンの供給源として、海藻も陸上植物も共生細菌を活用している可能性も大いに予想される。最近の学術雑誌(Nature誌)に、生きている高木の内部には多様で独特のマイクロバイオーム(木質部に1兆個の細菌)が存在し、森林生態の維持に寄与しているとの論文が掲載されていた。共生細菌は「形」や生長のみならず、植物に害虫や病原菌に対する免疫機能も与えているとのことである。地球上の生物は種間の共生なしでは生存していけないことを物語っている。このことは私の座右の銘「均一な社会は必ず滅びる」ともよく一致しており、生物多様性の重要性を指摘している。生化学を専門とする浅学の私にとっては、海藻の「形」は理解するには未知の部分が多く、深みのある領域であることがよく分かった。しかし、海藻における共生細菌や共生細菌が作りだす化学物質に関する研究分野は今後の有望な応用展開領域であることもよく分かった。何事も「形から始めよ」は茶道や武道に限ったことではなく、本エッセイが海藻の「形」から始まる「吉」となることを期するしだいである。
Y. Matsuo et al. (2005): Science, 307, 1598.
T. Wichard (2023): Semin. Cell Dev. Biol., 134, 69-78.
木下優太郎(2024): 藻類(Sôrui), 72, 169-174.
執筆者
堀 貫治(ほり・かんじ)
一般財団法人海苔増殖振興会評議員、広島大学名誉教授、農学博士