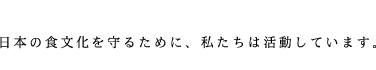産地情報 | 産地リポート
 後継者の育成が急務
後継者の育成が急務
全国で3桁の漁家が廃業しています。その大きな原因は後継者が育たないことです。もちろん子息など漁期中に家族労力の一人として手伝っている姿を見ますが、寒中の養殖作業に見合う収入になっていない現実を見ると、後継者としてのり養殖漁業の家業を継ぐより「他の仕事についた方が良いのではないか?」と自問自答することが多いようです。
各産地では、毎年漁期終了後に県毎に傘下漁家を招いて研修会を実施しています。内容は、その年度の養殖結果と問題点、さらに次年度養殖の注意点などが研究所の研究者、流通専門家によって、業界の課題、問題点、将来予測などについて語られています。

各産地で行われる漁期終了後の研修会
後継者の出席も多いのですが、現実には、当面する課題が多く、将来どのよな産業にしなければならないか、産業としての発展を押し進めるために何をなすべきかについて語られることが少なく、研修会の休憩時間が終わると会場に空席が増えるようです。
研修会では、如何においしいのり作りを行うか-と言うことが基本テーマですが、現在の流通システムを継続することを前提にした「おいしいのり作り」である以上、手間を掛けておいしいのりを生産しても、おいしいのりとしての価値が認められて産地価格が上昇するような流通システムであれば、耳を傾ける熱心な姿も多くなりそうな気配が感じられるのです。
後継者が意欲を持ってのり養殖漁業に取り組むためには、いくつかの要素が考えられるでしょうが、一つは、自信作を直接消費者に食べてもらい味の評価とそれに対する価値(値段)の評価を消費者の表情をとおして汲み取ることが生産者にとっては製品作りへの大きな励みにもなるのではないでしょうか。
もうひとつ考えられることは、文部科学省の推進企画として、平成17年に産学連携高度人材育成推進委員会の第1回会合が開かれ、以来各大学でこの制度に関係した活動を行っています。この委員会の目的は「大学と産業界がパートナーシップを形成し、産学連携による高度専門人材の育成を行い、大学の人材養成機能の充実・強化を図る事業を円滑に推進するため、産学連携による高度人材育成の推進の在り方等の検討を行う」というものです。
このような制度を活かした活動で、学生たちと地元後継者との交流を図ることによって、若い人たちの考えを活かした将来ののり養殖漁業の在り方を探るる手立てを知ることにもなり、それ以上に産地の若い人たちとの交流によって外部から見たお互いの姿を見つめ直す機会を得ることが出来るのではないでしょうか。
まだ本格的な動きではないと思いますが、3年前から佐賀県有明海漁協の佐賀市支所が、早稲田大学との間ですでに実践しています。佐賀市は早稲田大学の創始者・大隈重信侯生誕の地でもあり、同大学の卒業生による同窓生組織「稲門会」の地元会員も陰ながら応援しているようです。時間を掛けて続けることが大切です。

のり製造工場でのりの検品を手伝う女子学生
今年も2月16日から20日まで女性3人を含む6名の学生が応募して参加しました。16日から21日まで佐賀市内の漁家にホームステイしてのり養殖と製造の実体験をしました。期間中の19日は佐賀市支所ののり集荷、検査場の手伝い、20日は佐賀市支所が借り受けている富士町市川の山間地で海を育てる植林作業を行なうなど、のり養殖漁業の実体験をしました。
3人の女子学生は、早稲田大学人間科学部2年生(愛知県出身)、商学部3年生(神奈川県出身)、大学院経済学部修士課程1年生(中国出身)でした。
参加した女子学生3人にお会いし、参加の動機をお伺いしましたが「私たちの日常の生活にない姿を体験することは大切であると考えたためです」と前向きな動機であることを聞くことが出来ましたが、話を聞く中で現代の女子力の強さを感じ、頼もしい思いでした。

早稲田大学学内誌
しかし、このような活動をのり生産県単位での支援で毎年見られるようになり、立場、考え方の違いの交流の中から産地後継者とのつながりによる新たな活動が発見出来れば、今後の海苔産業の発展を真剣に考える道につながるのではないでしょうか。
3年目を迎えた佐賀市内ののり産業体験者の一人が佐賀支所に立ち寄り、「来年も応募しますので、よろしくお願いします」と声を掛けて東京に帰ったそうで、電話での取材だったのですが、支所の事務責任者の声は大変嬉しそうでした。
学生が所属する学部を問わず、非日常の体験から産業の新たな発展に繋がる意見が出るかもしれません。今後ののり産業は今の後継者たちが背負って行くもので、旧来の経験が通用するものかどうか疑問です。「温故知新」という言葉もありますが、それは若い人たちが学んで行く中で気づくことで、海況の変化や消費状況の変化が激しい現況から将来を察して経験を積んで進むようになるのが、今後の在り方ではないかと思います。

その意味でも「産学連携授業」についてのり産業界でも積極的に関心を高め、連携を深める必要があるのではないでしょうか。